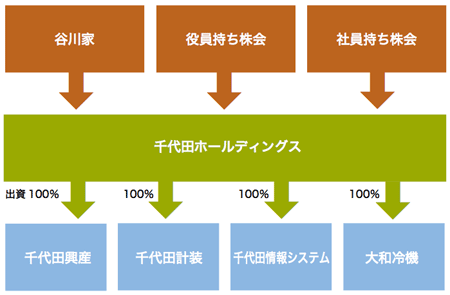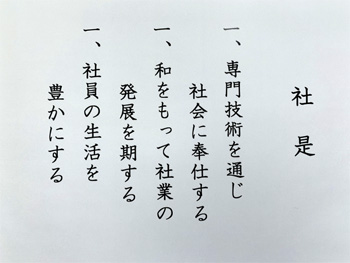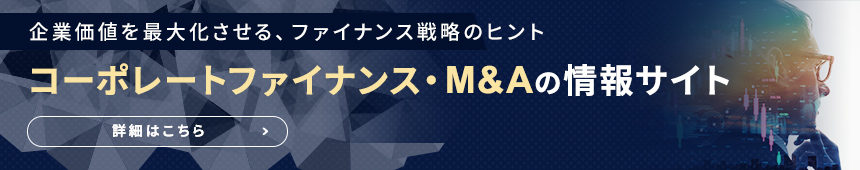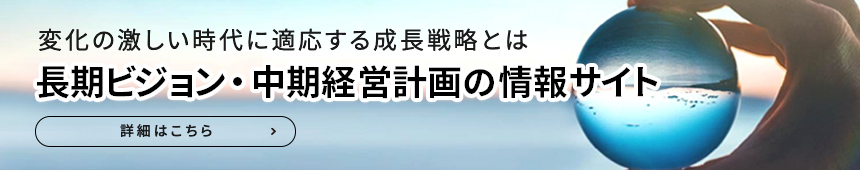千代田ホールディングス:オーナー、役員、社員による合議制経営へ、ホールディング経営導入で100年企業を目指す
福岡県に本社を置き、電気通信や空調計装、情報を中心に事業を広げる千代田ホールディングス。2015年、創業60周年を機にオーナー経営からの脱却を図るため、グループ会社を再統合する大胆な組織変更を断行。オーナー、役員、社員による合議制経営を目指して新体制をスタートさせた。
オーナー・役員・社員による三権分立の組織を構築
中須 千代田ホールディングスは、千代田興産、千代田計装、千代田情報システム、大和冷機をグループ会社に収める持ち株会社です。その始まりは1955年に創業された千代田電機(現千代田興産)にさかのぼります。まずは、これまでの経緯をお聞かせください。
谷川 父・雅雄が炭鉱に電線を販売する代理店として創業しました。1956年に日本電線(現三菱電線工業)の代理店となったこと、1960年にビルの空調設備を扱う山武ハネウェル(現アズビル)と特約店契約を交わしたことで事業が拡大。エネルギーが石炭から石油へと移行する流れに合わせ、電線やモーター、電灯、空調設備へと商材を広げながら順調に成長していきました。
その後、業務拡大を受け、1971年に計装部を独立させて千代田計装を設立。さらに2001年に千代田興産のコンピュータシステム部を、千代田情報システムとして分離しました。
中須 各社が専門性を高める形で分離独立を進めてこられました。それを再統合されたのはなぜでしょう?
谷川 以前から、「会社は誰のものか」について考えてきました。会社は「社会の公器」といわれる通り、オーナーが会社を私物化すべきではないと思います。私は社員を守るために会社を経営していましたが、本来は力のある人材が社長になるべきだと考えています。
ただ、社員が社長になる場合、経営者の個人保証は大変な問題ですから、千代田興産、千代田計装、千代田情報システムの3社を再統合するホールディングス化を決断しました。さらには2016年にM&A(合併・買収)を通して大和冷機がグループ会社に加わり、現在の形が出来上がりました。
中須 組織変更に伴って谷川取締役(前代表取締役社長)は所有していた株式をホールディングスに拠出し、役員持ち株会や社員持ち株会に充当されました。その理由をお聞かせください。
谷川 目的は、オーナー家の独断専行の抑止です。以前は、私と弟の幸雄を中心に谷川家が全株式の51%を保有していました。その比率を42%まで下げる一方、役員持ち株会を29%、社員持ち株会を29%まで引き上げました。
オーナー家と役員、社員の株式保有比率を近づけることで資本の三権分立を実現したのは、3者による合議制で経営する組織を目指したためです。
中須 資本構造だけでなく、組織面でも合議制による経営を明確にされています。
谷川 経営戦略の最高意思決定機関は千代田ホールディングスの取締役会に持たせています。取締役会のメンバーは同社の代表取締役社長と取締役によって構成されていますが、グループ各社の社長が取締役を兼任する形としました。社長の選出や経営方針の決定といった重要事項は、全て役員会で決めています。

千代田ホールディングス 取締役(前代表取締役社長) 谷川 進氏
1946年広島県生まれ。九州産業大学工学部卒業。1972年千代田興産入社。1985年取締役、1992年代表取締役社長。1997年千代田計装取締役、2001年千代田情報システム代表取締役社長。2008年千代田興産代表取締役会長、2009年千代田情報システム代表取締役会長、2011年千代田興産会長、2015年千代田ホールディングス代表取締役社長。2019年5月より千代田ホールディングス取締役、千代田情報システム代表取締役社長。

千代田ホールディングス代表取締役社長田中政利氏
1960年生まれ。佐賀大学経済学部卒業後、1984年佐賀銀行入行。2010年博多支店長、2012年福岡支店長、2014年唐津エリア長兼唐津支店長などを経て、2014年取締役、2017年取締役営業統括本部長代理、常盤商事専務取締役。2018年千代田ホールディングス副社長、2019年5月より代表取締役社長。
「令和」とともに新体制をスタート
中須 平成の終わりとともに谷川取締役は千代田ホールディングスのCEO(最高経営責任者)を退かれ、元号が「令和」に変わった5月1日から田中新体制がスタートしました。田中政利社長は銀行ご出身とお聞きしました。どのようなご縁で抜擢されたのでしょうか?
谷川 谷川家以外の人材から社長を選ぼうと考えていたので、以前よりお付き合いのあった銀行から来ていただきました。
任せたからには、私が前に出ることはありません。丸投げしているので大変でしょうが、中立の立場で会社全体をしっかりとまとめてくれると期待しています。
中須 田中社長は以前から千代田興産とお付き合いがあったのでしょうか?
田中 支店に勤務していた頃に何度も訪問していました。千代田興産は地域の優良企業ですから、以前から銀行内でよく名前を耳にしていました。ただ、2018年に入社してみると、業務が非常に多岐にわたっていることや、想像以上に財務がしっかりとしているので驚きました。
中須 良い意味で想像を上回る組織だったわけですね。
田中 一言で言えば、面白い会社。グループ会社の顧客はそれぞれまったく異なりますし、千代田興産だけを見ても地域や部署によって事業内容が違います。
例えば、東京は顧客企業に社員が駐在することもありますし、広島では調剤薬局を含めて手広く事業展開するなど非常に多様。何でもできる面白さがあり、やる気のある人にとっては、やりたいことに挑戦できる良さがあると感じました。
一方、千代田計装はどの拠点も業務内容は同じですが、高い技術を有する優秀な社員が多いので、今後も成長が見込まれます。
中須 同じグループ企業であってもそれぞれに個性があります。そうした違いをシナジーに変えて70年、80年、100年と会社を持続的に発展させていくには、共通の目的が必要になります。今は、田中社長を中心に中期ビジョンの策定を進めておられますね。
田中 新体制に移行するに当たって、まずは内部向けに「不易流行で100年企業を目指す」というスローガンを策定しました。もともと100年企業を目指す意識を強く持っていますし、ホールディングス化の後はグループが一体となるような研修を行ってきました。すでに人材は育っているので、その力を生かしながら年内にグループビジョンをつくり上げたいと考えています。具体的には、10年後のビジョンを考える次世代経営塾をスタートしており、ビジョンの策定と同時に経営者人材の育成にもつなげていきたいと考えています。
●持ち株会を組織・拡充し、企業価値を社員に還元
会社を成長させるのは社員、企業内経営者の育成を急ぐ
中須 社員がビジョンの策定に関わることは、全社的な視点や経営者の視点を持つ良いきっかけになります。また、社員教育については、チームコンサルティング対談以前から熱心に取り組まれておられます。
田中 会社を成長させるのは社員ですから、今後も人材の採用と育成には注力していきます。
まず、人材採用はこれまで以上に対応していく必要があります。従来は代理店として黒子のような立ち位置に徹していたことなどもあり、企業規模に比べて知名度が低いことは課題です。人材採用が難しくなっていますから、今後は千代田ホールディングスが、グループ会社も含めて魅力を発信していくことが重要だと思います。
一方、人材育成については、社内研修と社外研修を組み合わせて実施しています。定期的にタナベ経営の幹部候補生スクールに社員を派遣しており、参加した社員からは「異業種の方と交流ができて大きな刺激を受けた」など前向きな感想を聞いていますので、続けていきたいと思います。
中須 同じ立場の異業種の社員との交流によって、新しい発見があったり仲間ができたりするといった声は多く聞かれます。人材面で、ホールディングス化に伴って新たに検討されていることはありますか?
谷川 企業内事業家の育成は欠かせません。経営を経験させることが大事ですから、各拠点の分社化を進めていきます。まずは大分の事業所を分社化し、これをモデルに各拠点に広げていく予定です。幸い、「やりたい」と手を挙げている人材がいますから、非常に楽しみにしています。
中須 経営に携わることは、社員のやりがいにつながります。人材育成で言えば、2018年に「一般財団法人千代田財団」を設立されました。福岡県内の大学に在学し、機械工学、電気工学または情報処理を専攻する大学生に対して、返済不要の給付型奨学金を支給されています。非常に素晴らしい取り組みと言えますね。
谷川 当社は2020年に創業65周年を迎えます。長い間、福岡県に拠点を置いて活動させていただいたので何か恩返しをしたいと思い、これからの地域・社会を担う若い方を応援する財団を設立しました。今後は要件が整い次第、公益法人へ変更したいと考えています。
中須 貸与型の奨学金の返済に苦慮する社会人は少なくありません。給付型の奨学金によって学業に専念できるなど大学生の大きな助けになるはずです。優秀な人材が1人でも多く育つことは、地域経済や社会の発展にとって非常に意味のあることだと思います。
人材育成とM&Aで省エネソリューションに注力
中須 今後の注力分野については、どのようにお考えですか?
田中 省エネをビジネスの一つの柱にしたいと考えています。現在も千代田興産本社内(福岡市中央区)に設置された省エネソリューション部に約10名が在籍しており、鹿児島を筆頭に工事実績を増やしています。それ以外の地域においても、助成金が出る工場などの省エネ・CO?削減の調査を入り口として受注を増やしていこうと考えています。そうなると営業体制の拡大は不可欠ですから、人材採用やM&Aには今まで以上に注力していくことが必要になります。
中須 2016年にM&Aでグループ化された大和冷機も省エネの技術を持った会社でした。
谷川 良いご縁があって仲間に迎えることができました。大和冷機は40年以上の歴史がある管工事をメインとする会社。熱源の施工が強みで、資格を持つ技術者もそろっています。
財務面もしっかりしている優良企業ですが、後継者不在に悩みをお持ちでした。同じ地域で事業をしており、互いの思いが一致したことが良い結果につながりました。
中須 M&Aは足りない技術や人材を補う上で有効な手段になります。
田中 おっしゃる通りです。良いご縁があれば今後も挑戦したいと考えています。特に、ここ数年は省エネ・CO?削減につながる工場の改修ニーズが高まっていますが、今は外注に出さざるを得ない状況です。社内で完結できるようになれば事業が広がるため、M&Aも含めて投資をしていくことが必要だと考えています。
谷川 地域経済から見れば、M&Aで良い企業を残すことも一つの社会貢献の形ではないかと思います。技術があって財務内容が良い老舗企業であっても、後継者難や人材採用難から廃業を選ぶケースは少なくありません。そうした企業がM&Aで存続した結果、買収側にとって多角化などのメリットがあるのならば取り組むべきだろうと思います。
谷川イズムを継承しつつ新体制で成長を目指す
中須 千代田ホールディングスは、創業者・谷川雅雄氏の代に売上高41億円、2代目の井出清氏の代に100億円を突破。さらに3代目の谷川取締役の代は200億円規模まで成長するなど、九州を代表する企業へと飛躍されました。100年企業に向けて持続成長していくために受け継いでいきたいことはありますか?
谷川 創業者の時代から技術力に高い評価をいただいたことが現在につながっています。加えて、お客さまの声を聞き、ご要望に精いっぱいお応えしてきたことで事業が広がってきたのだと思います。
創業者が電線やその先にあるモーター、空調設備へと事業を広げて技術商社モデルを確立した後、2代目社長の井出は既存事業にこだわらず、ソニーと一緒にブラウン管テレビの工場を設立したり、TOTOと水洗トイレの電源を共同開発したりと付加価値の高い新規事業によって会社を飛躍させました。これまでの志を引き継いで、社員には既成概念にとらわれずに挑戦してほしいと思います。
また、グループ会社の社長は、自らお客さまを訪問してご要望を聞き、それに応えていくことを心掛けていただきたい。それ以外に、成長する方法はないと私は思います。
中須 田中社長が新体制を引っ張っていくことになります。トップに立つ抱負と今後の展望についてお聞かせください。
田中 グループ全体で社員数は約320名。家族を含め1000名以上の将来を背負っているわけですから、失敗は絶対に許されません。当然、今以上に成長していくことが目標です。ただ、各社の社長を務める役員は谷川イズムをしっかりと継承していますから、間違った方向に行くことはないだろうと感じています。
次の社長はおそらくプロパー社員から誕生するでしょうから、しっかりと橋渡しできるように谷川取締役の思いを受け継ぎながら、ホールディングス体制を整えていくことが私の役割だと考えています。
中須 令和を迎え、新体制として動き出した千代田ホールディングスがますます飛躍され、100年企業として持続的に成長されるよう全力でサポートしてまいります。本日はありがとうございました。

タナベ経営 経営コンサルティング本部 副本部長 中須 悟
「経営者をリードする」ことをモットーに、経営環境が構造転換する中、中堅・中小企業の収益構造や組織体制を全社最適の見地から戦略的に改革するコンサルティングに実績がある。CFPR認定者。著書『ホールディング経営はなぜ事業承継の最強メソッドなのか』(ダイヤモンド社)
PROFILE
- 千代田ホールディングス㈱
- 所在地:福岡県福岡市中央区白金2-5-16
- 設立:2015年
- 代表者:代表取締役社長 田中 政利
- 売上高:194億円(グループ合計、2019年4月期)
- 従業員数:320名(グループ合計、2019年4月現在)