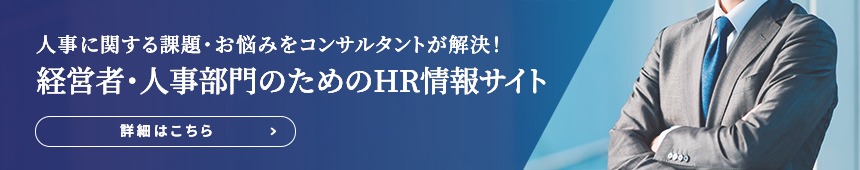店は劇場、店員は劇団員、顧客は観衆。いつも「良質な外食体験」を:銚子丸
変わりゆく食文化への一手として、2019年に始動したのが新ブランド「銚子丸 雅」だ。初の商業施設内のテナント出店で、全ての注文はタッチパネルで行う。座席もボックス型を採用し、周囲を気にせず握りたてを味わえる。職人が目の前で握る都心型のコンパクト店「鮨 Yasuke(すしやすけ)」も1号店が始動した。
新事業の「出張回転寿司」サービスも好評だ。老人ホームやパーティーなどに出張しその場ですしを握る。新事業だが宣伝しなくても1000人規模の企業イベントなど、月に十数件を受注。法人需要を発掘し社会貢献にもつながる新事業として、数年後には事業子会社化する計画だ。
「他にもやりたい、やらなきゃ、と思うことがたくさんあります。各地の漁港近くで、取れたての魚を味わえる店。ペット同伴でも堂々と楽しめる店。画期的だな、と思える回転ずしを実現できたら」(石田氏)
異なる食材を扱う多角化も視野にある。自社開発だけでなくM&A(合併・買収)やアライアンス(事業提携)も選択肢に入れ、すしを基軸にその周辺へと広がる、新たな食のシーンへの挑戦だ。食材の違う新事業はリスクヘッジの狙いもあるが、変わりゆく食のシーンに自らが主体的に関わっていく楽しみがある、と笑顔で語る石田氏。その胸中には、秘めた熱い思いがある。
「銚子丸が繁盛したことで、街のおすし屋さんが消えていったのは事実。でも、そこで終わらないことが大事なんです。9000億円規模のすし市場で、回転ずしは約6000億円。当社のようなグルメ回転ずしはその25%で、残りは大手100円回転ずしチェーンです。さらに台頭を許すと、これから生まれ育つ日本人は『すし=100円ずし』になってしまいます。本来の、街の江戸前ずしを受け継ぐ銚子丸が、その姿を守り抜くこと。さらに、とんかつやウナギ、天ぷらなど日本の伝統的な外食文化の灯も消さないように。未来の顧客に通じる銚子丸でありたいと願っています」(石田氏)

銚子丸 代表取締役社長 石田 満氏
Column
理念を旗印に、サステナブル企業を追求
銚子丸が卓越した企業となり永続していくために、石田氏が創業者から託された思いがある。
「すしを売ろうとしなくていい、理念を売ってほしい」――。これは真心を提供し、顧客の感謝と喜びをいただくことを使命とすることを指す。
起業家として「売り上げ最大、経費最小、利益は極大値」を追求する中で、その原資は「顧客に喜んでもらわなければ生まれない」と気付いた創業者が、社員の心にも刻もうと定めた経営理念だ。「理念を旗印に、どうすれば顧客が喜ぶかを考え続ければ、食のシーンや喜び方が変わっても、正しい方向へと歩みを進められます」と石田氏は語る。
新サービスの「出張回転寿司」で老人ホームへ出向くと、利用者は涙を流して喜び、笑顔で礼を言う。店舗ではあり得ない光景に「それこそが理念を売る、ということ」と、石田氏。サステナブル(持続可能)な自社像を追求するのも、理念を実現するためだ。商品・人・場のQSCの質を高めれば顧客満足度が上がり、売り上げが伸び、利益も生まれる。そして、支払いや投資の余力ができ、さらなる質の向上を推進できる。その好循環サイクルを回すのが、銚子丸の未来形である。
「経営理念は、原点回帰で昔に戻るのではなく、形になる姿を進化させていくもの。当社は100年企業を目指していますが、100歳の姿で永続したいわけじゃない。絶えず挑戦し、生まれ変わって若々しい会社であり続けていきますよ、これからも」(石田氏)
PROFILE
- ㈱銚子丸
- 所在地:千葉県千葉市美浜区浜田2-39
- 創業:1977年
- 代表者:代表取締役社長 石田 満
- 売上高:193億1600万円(2019年5月期)
- 従業員数:495名(アルバイト・パート除く、2019年5月現在)