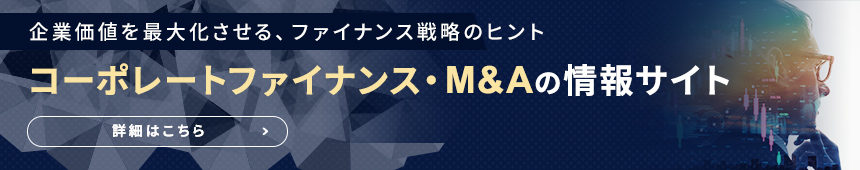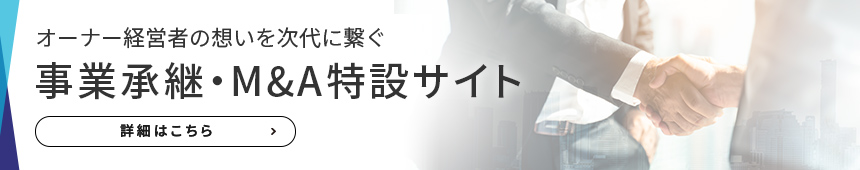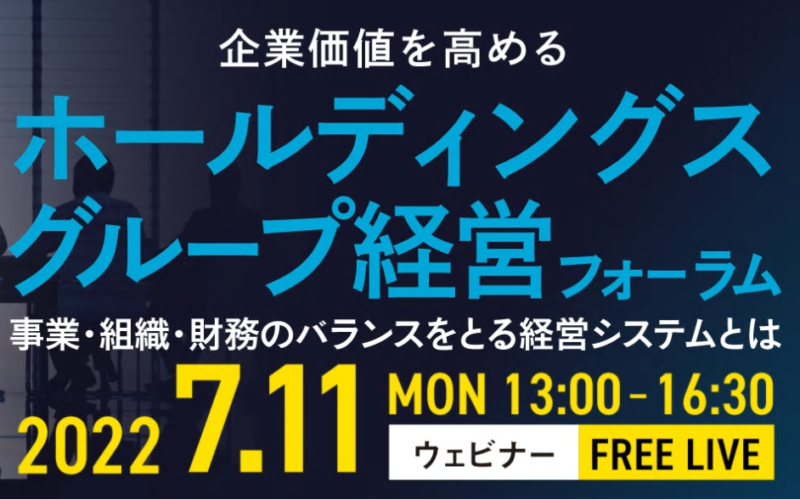グループ企業で人材の最適化を図る:ヨシムラ・フード・ホールディングス
高度経済成長期、その原動力となったのが中小企業だったことは、あらためて言うまでもない。もちろん食品業界も例外ではなく、若い社長の旺盛なバイタリティーにけん引され、多くの会社が競い合って成長してきた。しかし、市場の成熟とともに、その多くが衰退しかけている。
「衰退している企業、そこに勤めている人をどう救い上げるか。その社会的ニーズは極めて大きい。国の政策課題と言ってもおかしくないと私は思っています。かといって、助成金を出したのでは、さらに台無しにしてしまう。伝統のある会社、ベテランの社員を、新しい時代にどうソフトランディングさせるか――。当社の仕事は、その一例だと思っています」
およそあらゆる産業は、当初は家族経営やベンチャーのような小規模経営でスタートするが、イノベーションが起こることによって、誰もが手軽にその恩恵を得られるようになり、市場として成熟していく。
そのイノベーションによって、消費者は多大な恩恵を被ったが、従業員には失職する可能性が生まれ、新たなスキルを身に付ける必要性も生じた。
現代の食品業界におけるイノベーションは、量販店やスーパーマーケットの巨大化だったと吉村氏は言う。資本力を背景に巨大な小売店が現れ、合従連衡しながら成長した。あらゆるものが安くそろうこれらの巨大小売店は、製造側の中小企業にとっては大変な脅威となった。あまりの力の差から、値段交渉の余地が与えられなかったり、スーパーのプライベートブランドを生産するうちに商品開発力を失い、疲弊してしまった企業もある。
「儲からなければラインを減らしたり、廃業して次の道を探すのが欧米流ですが、日本の中小企業には“お家大事”とでも言うべきマインドがあって、家業だからこのラインは止められない、赤字を出してもこの味は守る、となりがちです。社長にとってはそれでよいかもしれませんが、付き合わされる社員や後継者の家族にとっては、ダメージが大きい。若くて、カリスマ性に満ちた社長なら、そんな状況でも社員はついてきたでしょうが、年をとればどうしてもその力は失われてしまいます。だからこそ、資本と経営は分けた方がいいと思うのです」
同社の目下の課題は、人材育成だという。
「商品開発ができる人材や、ラインを管理できる人材は、グループ各社から何人も探してくることができます。しかし、事業を支援し、プロジェクトを完遂させることのできる人材は、育成しなければ現れません。今は、ポテンシャルのある人間が大企業や官僚に偏り過ぎています。若い人がプロの経営者、オーナーとして企業のかじ取りをしてみたいと思うような成果を出していくことが、当社の課題でしょうね」
PROFILE
- ㈱ヨシムラ・フード・ホールディングス
- 所在地:東京都千代田区内幸町2-2-2?富国生命ビル18F
- 設立:2008年
- 代表者:代表取締役CEO 吉村 元久
- 売上高:237億1600万円(連結、2019年2月期)
- 従業員数:1019名(2019年2月末現在)