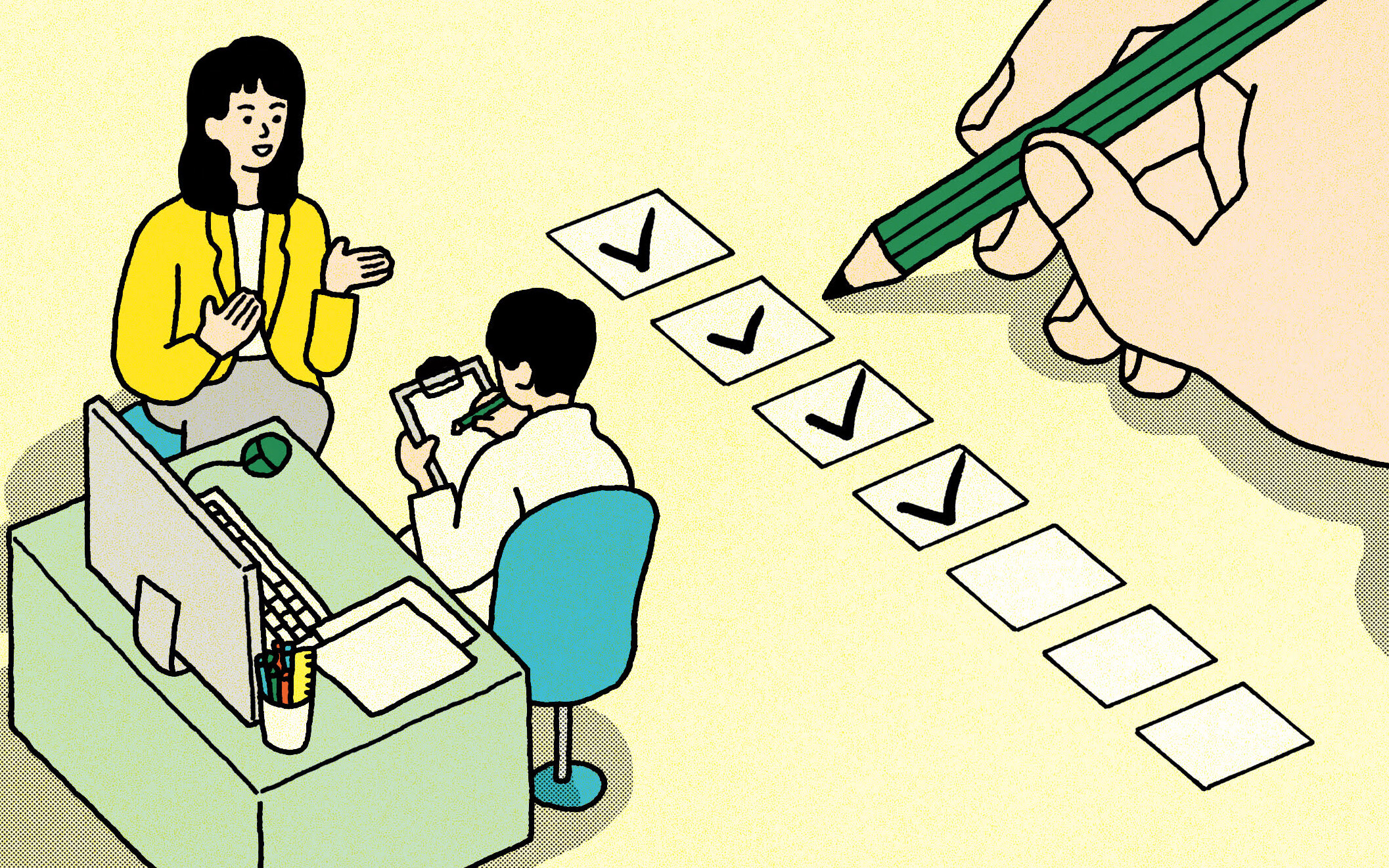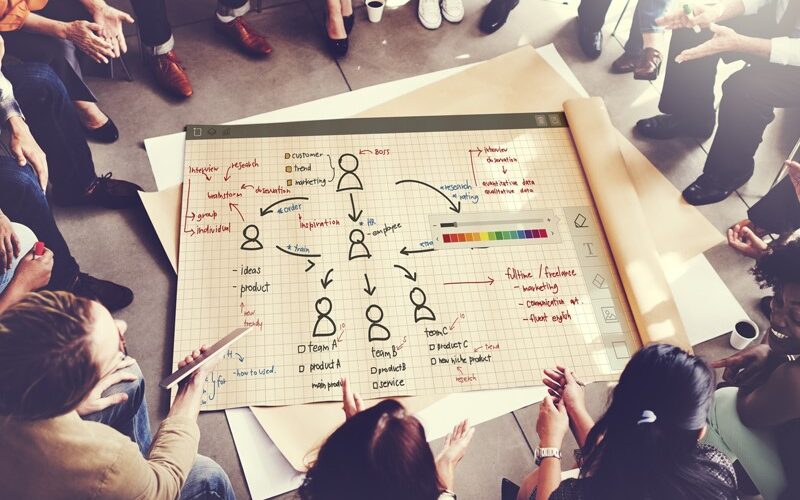Vol.4 ストレスを軽減する生活習慣
ストレスの性質
「ストレス」という言葉から何をイメージされるでしょうか。「不快なこと」「苦手な人」「慣れない場所」など、ご自身にとって「嫌だな」もしくは「苦痛だな」と感じることを思い浮かべる方が多いのではないかと思います。ですから、できる限り排除したいものと認識されている方も多いかもしれません。
そもそも、ストレスとはどういうものなのでしょうか。私たちの心身は、常に一定の状態を保つ「ホメオスタシス機能」が備わっています。例えば、全力で走った後に心拍数が一時的に上がりますが、時間を置けば元の状態に戻ります。同じように、心も何かしらの変化により刺激を受けた状態からホメオスタシス機能が作用して、通常モードに戻ろうとします。
その元に戻そうとする力のことをストレスと呼び、それを作っている原因を「ストレッサー」と呼びます。
このストレッサーは、自身に起こる「変化」がもたらすもので、不利益なものだけに起因するわけではありません。つまり、良いことも楽しいこともストレスの原因になります。
人生には、結婚や転居、身近な人の死など、大きな変化を伴うライフイベントがたくさんあります。環境や状況を大きく変化させるこうした出来事が過大ストレッサーとなるのです。
職場においては、昇進・昇格、部署・担当替えなどがストレッサーとなります。たとえ希望していた仕事に就けるとしても、心に負担が掛かるのです。ストレスケアは「自分の置かれている環境や状況に変化が起こった時」に必要なのだと心に留めておいてください。
変化に潜む職場の不調
5月ごろに起こる心身の不調状態を総称して「5月病」と呼びます。なぜ5月に心身の不調が起こるかというと、3、4月は年度替わりで最も変化の多い時期に当たり、その時期にストレッサーが多く存在するからなのです。みなさんの職場でも、3月には人事異動に伴って引っ越しがあったり、4月は新入社員を迎えたり、社内制度が変わったりして、とかく忙しい時期ではないでしょうか。
忙しいと、普段行っているストレス解消法を実施する時間も持てずに、ひたすら変化の影響を受け続け、気付いた時には心身ともに疲弊して動けなくなっているという状況になりやすいのです。要するに、変化の多い時期をうまく乗り切れなかった結果でもあります。年度の変わり目だけでなく、職場や生活環境に変化があった際は、ご自身はもとより、部下の状況を把握し心配りをしていくことが重要でしょう。
ストレスと付き合う
生きている限り変化を避けることはできません。私たちは常にストレスにさらされています。しかし、ストレスが少ないとモチベーションが下がる原因になるため、適度にある方が望ましく、生きる活力になります。ストレスはなくすのではなく、「うまくコントロールする」という意識で付き合っていただけたらと思います。
ストレスを緩和するための解消法については、本連載の第2回(2019年10月号)でも触れましたが、今回は気持ちをコントロールしやすくなる日常生活の過ごし方についてお伝えします。
感情や気分のコントロールのためには、俗称「幸せホルモン」とも呼ばれている神経伝達物質、「セロトニン」を脳内で充足させておくことが大切です。セロトニンはモチベーションを維持するのに欠かせません。うつなどの症状を改善させるために処方される薬は、主にセロトニン調整を行うものであることからも、その重要性が分かります。
打たれ強く柔軟性のある精神を育むためにも、日々の生活の中でセロトニンが多く分泌される習慣を取り入れていきましょう。
心掛けたい生活習慣
セロトニンは体内で生成できないため、食べ物から取る必要があります。原料となる必須アミノ酸のトリプトファンを含む食品を取ることが望ましく、牛乳、ヨーグルト、チーズなどの乳製品、納豆や豆腐など大豆製品、また、バナナやナッツ類にも含まれているので積極的に摂取してください。
イライラした時は、ブラックコーヒーではなくカフェラテにするなど工夫しながら取り入れるとよいでしょう。食事はバランスも大切なので、他の食品も含めて偏りなく取ることを忘れないでください。
効率よくセロトニン分泌を促すためには、1日20~30分のリズミカルな運動を心掛けましょう。駅やオフィスの階段を昇降したり、一定のテンポで早歩きしたりすることでも効果を得られます。
気を付けたいのは、2日間以上の連続した休日です。土日休みの仕事の方が月曜日にゆううつな気分になる原因の一つは、週末に体を動かさずに過ごすことにあります。1日くらいはのんびりと過ごしても問題ありませんが、その他の日は体を動かすようにしましょう。特に、車移動の多い方やオフィスワークの方は、意識して運動を取り入れてください。
生活習慣のポイントとして、陽の光を浴びることも大切です。冬場は日照時間が短いため、暗いうちに家を出て暗くなってから帰途に就くことも多いでしょう。ランチタイムに外へ出るなど、ちょっとした合間の日光浴を心掛けてください。
適切な入眠は起床時間がポイント
リーダーはとかく忙しく、睡眠時間を削り十分な睡眠を取れていない方も多いのではないでしょうか。心身ともに健康に過ごすためには睡眠が重要だと分かっていても、毎日決まった時間に休むのは難しいかもしれません。そういった場合、休日にしっかりと睡眠をとり、その週のうちに体調を整えるよう心掛けましょう。
眠り過ぎて睡眠のリズムが狂った時は、入眠したい時間から逆算して16~18時間前に起きることをお勧めします。起床して16~18時間後が一番入眠しやすい時間帯だからです。例えば、22時~0時に眠りたい方は6時に起床すると比較的スムーズに眠りにつきやすくなるので参考にしてください。
ストレスをコントロールするための生活習慣を身に付け、リーダーとしてのセルフケアはもとより、従業員や部下への意識付けにも活用していただければと願います。