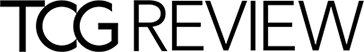Vol.70 「わずか5本」からの攻勢:日興エボナイト製造所

日興エボナイト製造所「笑えぼや暮屋」の万年筆
エボナイトは黒く硬い樹脂で、ゴムにイオウを混ぜ加熱して作る。人間の手になじむ独特の肌触りが特長
日本で「唯一」の町工場
オリジナルの万年筆作りが町工場を救ったという話をします。
東京都荒川区の日興エボナイト製造所は、エボナイトという天然ゴム由来の樹脂を製造する工場です。
1952年に同社が創業した当時、エボナイトを作る工場は全国にいくつもあったそうです。ところが現在では、エボナイトを製造するメーカーは日本で同社だけになりました。世界規模で見ても、エボナイト工場はもう数えるほどしか残っていないらしい。
理由は明らかで、石油由来のプラスチックに完全に押されたからです。それでも日興エボナイト製造所が転業しなかったのは、現社長である遠藤智久氏の祖父による言葉があったからだそうです。
「祖父は『お客さんがいる限り、エボナイト製造はやめない』と繰り返し話していました。それを私も守っているわけです」(遠藤氏)
日本でただ1つしかないエボナイト工場ですが、電気絶縁素材や楽器のマウスピースとしての需要は一定にあります。エボナイトが天然ゴム由来であるからこその特性が、そうした用途を生んでいました。とはいえ、これらの需要に頼るだけではジリ貧になるのは目に見えていましたし、実際に業績はどんどん下がっていきました。
日興エボナイト製造所の万年筆は、2009年に第1号を登場させたいわば新規参入組です。国内外の既存ブランドに太刀打ちできるのか、厳しい戦いになるのではないかという見方もありました。ところが、多くのマニアがこの万年筆に振り向いています。
売上減少傾向から回復
先に、売り上げの推移をお伝えしますと、遠藤氏が家業に入った1990年代後半には売上高1億円を割って8000万円規模に縮小していました。その後も低落傾向に歯止めがかからず、約3000万円にまで落ち込んだ。これはもう存亡の危機です。
ところが、2009年に初めての自社ブランドとして万年筆を発売して以来、売り上げ下落は止まって、さらに反転の兆しを見せ始めました。現在では、社長が入社したころの8000万円ラインにまで回復。その25%ほどが万年筆の事業によるものだそうです。これはすごい話だと、私には思えました。
万年筆の名は「笑暮屋(えぼや)万年筆」。その価格は3万4100円(税込み)からです。
なぜ万年筆だったのでしょうか。エボナイトの需要は、電気絶縁素材やマウスピースの他にもあって、例えば万年筆のペン軸に使われてもいました。同社は文具メーカーにもエボナイトを供給していたんです。触感がよく、また耐久性にも長けているので、万年筆メーカーはエボナイトをペン軸に用いたようなのです。
遠藤氏は2000年代後半に、工場の今後を考えに考えました。そこから出てきたのは、まず「脱・下請け」を模索すること。次に「BtoCで直接に消費者と結び付く事業の立ち上げ」でした。エボナイト市場が縮小の一途をたどる中で、下請け仕事だけでは展望が開けない。どうにかするには新たな領域に自ら踏み出さないと、という決断です。
では何を作るのかと思案した末に思い立ったのが、万年筆。
「万年筆という考えにたどり着くまで、ギターのピックやハンコの素材、あるいは杖といったふうに、いくつものアイデアが浮かびました。その1つが万年筆だったんです」と遠藤氏は振り返ります。
納入先の1つに万年筆職人がいたことが、ある意味で決定打となったようです。この職人から知恵を授けてもらえるという幸運に恵まれました。でも、ただ単に幸運とは片付けられません。
この職人へ相談するに当たって、遠藤氏はマーブル模様を描くエボナイトをわざわざ試作しました。それまでは黒基調の一辺倒だったのですが、それではいけないと思ったそうです。そしてマーブル模様のエボナイトを職人のもとへ持参して、万年筆製造の可能性に対してアドバイスを得ました。
「5本」に光を見いだした
2009年、遠藤氏は荒川区の産業展に、完成した万年筆をひっさげて参加します。
「当時、1本6万円の値付けをした万年筆が、2日間の産業展で5本売れました。つまり30万円の売り上げです」(遠藤氏)
5本という販売数、これは多いと見るのか、少ないと捉えるのか。
「予想以上の結果でした。うれしかった。これは商売としてありだと判断しましたね」(遠藤氏)
ああ、ここが分岐点だったのか、と私には思えました。わずか5本と考えるか、見事に5本もと踏まえるか。遠藤氏は後者でした。
「当社の出展情報を、万年筆好きな知人から聞き付けた人たちがわざわざ会場へ来てくれたんです。『手づくりのエボナイト万年筆が販売されるぞ』と」(遠藤氏)
遠藤氏はこうした流れに、万年筆事業の可能性を見いだしたんですね。万年筆には必ずやマニアを突き動かす要素があるというふうに。
産業展に出展した2009年、遠藤氏はウェブサイトを構築して、ネット通販で万年筆を正式に取り扱い始めます。このときの中心価格帯は1本5~6万円。
「でも、売り上げはさほどありませんでした。すぐに動きが出るとまではいかなかった」(遠藤氏)
では、どうしたか。荒川区の産業展で手応えを感じられたことを思い出し、イベントなどに地道に出展を繰り返そうと考えました。
そうした出展先に、百貨店のバイヤーが顔を出し、そこから大手どころの百貨店での催事に招かれ始めました。1週間の催事で多い時は200万円ほどの売り上げが立ったそうです。
同社は2014年、工場のすぐそばに直営店をオープンしました。
「ウェブ販売だけではなく店を持つのは大事、という判断からです。『店舗のあるブランド』という信頼感が備わりますから」(遠藤氏)
さらに、同じ2014年、海外の「ペンショー」への出展では、「日本からエボナイトの万年筆がやってくるぞ」と話題を呼び、ブースへの集客に成功しています。
「『ユニークな万年筆だ』という声が挙がったのが、印象に残りましたね」(遠藤氏)
エボナイトの素材屋が独自に万年筆を作ったというところが、注目を浴びた要因だったようです。
「ゴム屋が万年筆を作り始めて、もう10年以上ですよ」と遠藤氏は笑います。素材を扱う町工場が自ら万年筆を完成させた。ここにこそ、万年筆マニアの心をくすぐる理由があったのですね。
その意味ではまさに、足元にある宝物を生かし切って苦境を脱する契機をつかんだ好事例、と表現できるのではないでしょうか。