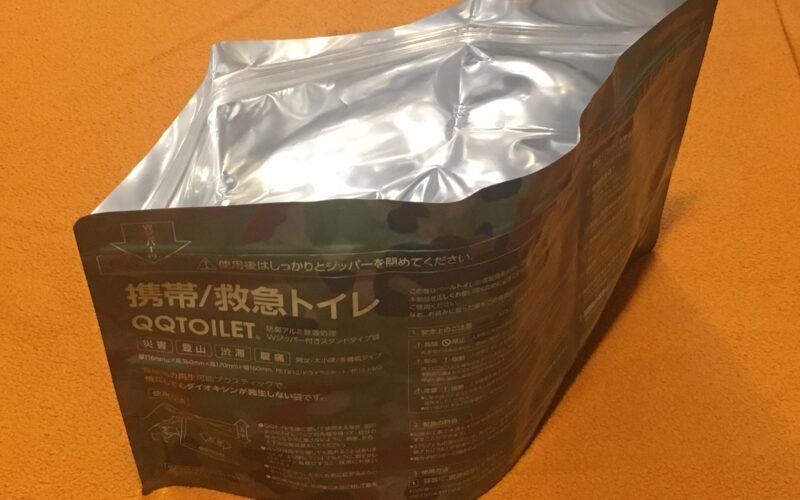Vol.57 誰が町を元気にするのか:富山市岩瀬


2020年3月21日、富山市のJR富山駅を挟んで南北それぞれ別に運行していた二つの路面電車が、線路の延伸により一つにつながった。直通運転の開始で、市街中心部から日本海に面する岩瀬までの移動が容易に。岩瀬は、古くは北前船の寄港地として栄え、今も廻船問屋だった建築物が残るなど、美しい町並みを擁している。
地元が対策を講じる
本連載の2016年7月号で「『町を元気にする』とは」というタイトルで、北海道・木古内町の話をつづりました。ちょっとだけ、おさらいをさせてください。
道南(北海道の南部)に位置する木古内は、長らく人口減少問題に直面してきた過疎の町です。
1980年代、青函トンネルが開通して、本州と北海道が鉄路で結ばれた時、木古内の住民は大喜びでした。念願だった特急列車が木古内駅に停車することになったからです。これで過疎化の問題は解消すると、地元は沸き立った。
ところが、事態は何も変わらなかったのです。「特急列車が停まるからもう大丈夫」と安心していただけで、町が賑わいを取り戻すには至らなかったという話。
2016年3月、今度は北海道新幹線が開業します。本州から新幹線に乗って北海道に上陸すると最初にある駅が木古内駅。さあどうするか。町の人々には、青函トンネル開通時の深い反省がありました。「ただ待っているだけではダメだ」「動かなければ町は賑やかにならない」と思った。
そして木古内駅の真ん前に「道の駅 みそぎの郷 きこない」を町挙げて開業させます。単に開業しただけではない。観光客も地元客も、そして新幹線で来た人も自動車で来た人も楽しめる趣向を凝らしに凝らした。
すると、この道の駅の来客数は、オープン3カ月で10万人を超え、最初の1年足らずで55万人を数えました。観光地ならいざ知らず、人口が4000人台の静かな過疎の町でこの成果です。大事な教訓を得られる話だと感じられました。
交通インフラの進展があったとしても、地元がそれを生かす策を講じなければ、思い通りに事は運ばない。口を開けて待っているだけではいけないということでもあり、逆に言えばこの局面で何が必要かを精査して動けば、交通インフラの整備が効果をもたらすのだと、木古内の事例は示していると思います。
南北の路面電車が直通化
私がなぜ、この木古内の話を今、思い出したか。2020年3月、北陸の富山市で、鉄路を巡って新しい動きがあったからなのです。
富山市には二つの路面電車がそれぞれ運行していました。ちょうど、JR富山駅を挟む形で分かれている格好です。駅の南側は、大正時代から根付いている、通称「市電」です。こちらは富山地方鉄道による運行。そして駅の北側は、もともとJRの支線だったものを一部路面電車化して、2006年に開業した「富山ライトレール」。第三セクター方式(以降、三セク)での運営でした。
前者は市内の中心繁華街と富山駅や地元大学をつなぐ路線です。後者は富山駅から日本海に向かって伸び、終着は岩瀬という町です。この岩瀬の話が、今回の本題なのですが、その説明はまた後ほどいたします。
さて、この二つの路面電車、2020年3月21日に富山駅の駅舎を貫く形で線路がつながりました。線路がつながっただけではなく、三セクだった富山ライトレールは富山地方鉄道に吸収合併され、名実ともに路線が一本化されました。
これによって、富山の中心エリアから海に面した岩瀬の町まで、乗り継ぎなしで行き来できるようになったのです。この富山に限らず、JRの駅の両側で町が実質的に分断されたような状況になっていて、それが都市形成の課題として横たわっている地方ってありますよね。そこに文字通り風穴を開ける役目を果たすと期待されたのが、富山の場合、二つの路面電車を直結するという事業でした。
ただし、線路がつながったからといって、劇的な変化を巻き起こせるとは限りませんね。かつての木古内と同じ話です。
さあ、ここからです。岩瀬は何を成したのか。もちろん、今回、ここで取り上げるからには、路面電車の直通化だけに全てを賭けて、後は何もしなかったという話では当然ありません。

地元の酒蔵による「沙石(させき)」。約100種の日本酒を立ち飲みできる(左)「つりや東岩瀬」。洒脱な宿泊用客室をしつらえる(右)
「見る」から「生かす」へ
この岩瀬という町は、江戸時代から明治時代にかけて、北前船が寄港する地として栄えた地域でした。廻船問屋だった建築物をはじめ、風情ある家屋が今も残り、古い町並みは魅力をたたえています。とはいえ、全国各地の古都のように、幅広い人たちが押し寄せるといった、観光地というほどの存在ではなかった。
では、この町はどう動いたか。岩瀬に生まれ育った1人の地元名士が、最初に旗振り役を買って出たのです。日本酒の蔵を営む、桝田酒造店の当主が、2004年に設立された「岩瀬まちづくり株式会社」の社長に就き、先導してきました。
彼が中心となって、岩瀬の街に魅力を加えるべく活動が続いたのですが、根幹に据えたのは「文化財を『見る』ものから『生かす』形に変える」という大方針でした。
どういうことか。単に歴史的建造物を売りにするのではなく、そうした存在を現代で輝かせ、さらには県内外の観光客を招く仕掛けとして活用しようとしました。「見る」から「生かす」への発想の転換を実行しようと、具体的には実力派の料理人や伝統工芸作家などさまざまな人物を岩瀬に招聘し、彼・彼女らの息遣いを感じさせる町へと変えました。


土蔵を生かした造りのクラフトビール蒸留所「KOBO Brew Pub」(左)「御料理ふじ居」。富山で超人気を誇る名店が岩瀬に移転した(右)
散策だけではない魅力を
登録有形文化財の米蔵は、クラフトビール蒸留所となり、まさに現代に蘇ったと感じさせます。また、町の中心を貫く道を行くと、そこには人気の日本料理店やすし店、イタリア料理店などが軒を連ねています。どれも、酒蔵の当主が折衝を重ねた末に、料理人や職人たちをここに招聘した結果と聞きます。
さらには、この町でそのまま泊まれるようにと、洒脱なしつらいの宿泊施設もできました。これは県内の事業者との協業によって実現した話でした。
ここで重要なポイントは二つあると思います。まず、そこにあるものをきちんと大事にした、という点ですね。一大観光エリアではないにせよ、ここ岩瀬には味わい深い建築物が立ち並んでいる。何もとっぴな策を採るのではなくて、何よりそこに光を当てようとした。
次に、人を招くには人の力があってこそだと考えたところでしょう。歴史をたたえた建物や町並みだけでは観光集客にはおぼつかない。そこに人の力(岩瀬の場合は、実力派料理人や工芸作家ですね)を合わせてこそ、この町の存在感が高まるのだという判断には、私も大いに賛同します。
酒蔵の当主は言います。「岩瀬に来れば、飲み歩き、食べ歩きができます。何軒もはしごしたっていい」。それも、風情ある町でそれがかなうのですから、確かに魅力がある。
当主が営む酒蔵自身も、やはり古い建物を生かす格好で、蔵の酒を低廉な値段でとことん飲み比べができる施設を2019年夏に立ち上げています。自ら率先して一肌脱いだというわけですね。
地域を元気にするのは誰か
ここであらためて思います。地域を元気にするのは誰なのか。
岩瀬の場合、地元名士である酒蔵の当主が先導役・実行役を担っています。彼の行動力がなければ、ここまで劇的な活性化は果たせなかったでしょう。一方、前述の木古内は、いわば団体戦でした。町も民間も、互いに力を合わせた。
ならば岩瀬の場合、1人のエースがいたからうまくいっただけの話なのか。いや、そうとも言えません。そのエース(酒蔵当主)の期待に応えた幾人もの料理人、工芸作家、また協力を惜しまなかった自治体の存在は外せません。
その意味では、やはり岩瀬も団体戦であるのです。そこを踏まえず、1人の有力者がいた幸運と捉えていては、町づくりのヒントを見逃してしまうかもしれません。