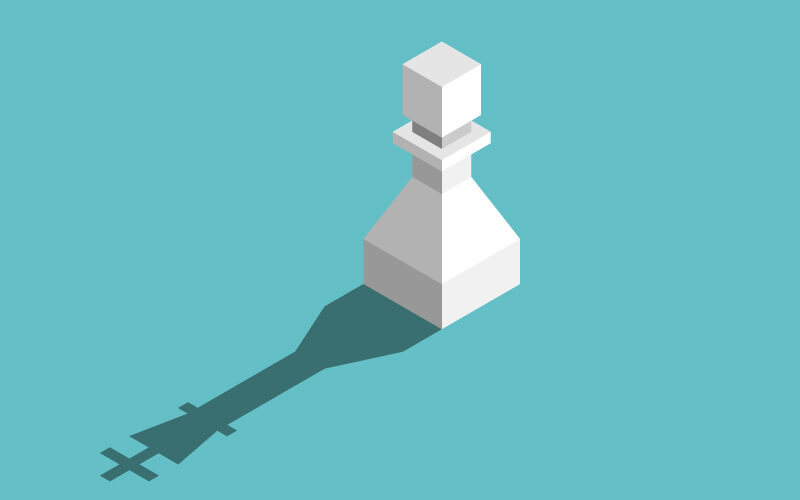テクノロジービジョンの構想で組織を変革する:森重 裕彰
コロナショックにより、猫も杓子もDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めている。数年前まで多くの企業の認識は、「DXができれば競合他社との差別化につながる」程度だった。しかし、今となっては、テクノロジーを取り入れていないことが「選ばれない企業」の原因になり得るほどに、デジタル化の重要度は高まっている。本稿では、長期視点でのDXの考え方や、取り組む際の着眼点について解説していく。
「DXは手段であって、目的になってはいけない」という言葉を聞くが、その通りである。どのような技術にせよ、課題を解決するための手段でしかない。だが、課題が見つかってから、手段としてのテクノロジーを考えるのでは遅い。取り組みの着手が遅くなることで、課題解決の領域が狭くなってしまうからだ。
私は、「Techno Driven(テクノドリブン)」という考え方を提唱している。テクノロジーを起点として、業界や自社の抱える課題をどのように解決できるかを検討する技術解決思考法だ。(【図表1】)
【図表1】「Techno Driven」の技術課題解決フレームワーク
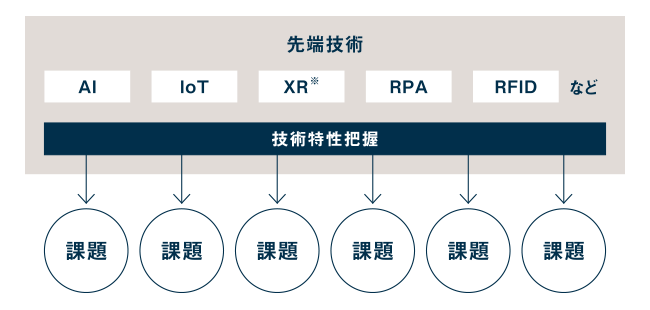
※VR、AR、MRなどの先端技術の総称
出所:タナベ経営作成
Techno Drivenを用いることで、1つのテクノロジーで複数の課題を解決することができる。例えば、高品質・低価格の衣料品を提供するユニクロやジーユーなどを傘下に持つファーストリテイリングでは、ここ2~3年で実店舗にセルフレジを導入し、「商品付加価値の上がらないレジ業務」の無人化に取り組んでいる。その裏側にあるのは、「RFID」という自動認識技術だ。RFIDとは、電波を用いて商品のタグデータを非接触で読み書きするシステムで、スキャナーをかざすだけで複数のタグを一括で読み取ることができる。
また同社では、このRFIDを用いて「棚卸作業の時間短縮」「倉庫の自動化」という2つの課題も解決している。このように1つの技術で複数の課題を解決することが、Techno Drivenを用いた課題解決フローの特長である。
DXへの取り組みが必須となった今、長期ビジョンにテクノロジーを軸としたロードマップを作成することをお勧めしたい。「テクノロジービジョンマップ(以降、TVM)」をチームで作成するのである。
TVMとは、3~5年スパンで自社に導入すべきテクノロジーを整理し、「どのような課題を解決したいか」などを検討するロードマップだ。TVMを作成することでDXを格段に速めることができる。取り組みの流れは次の3つである。
①テクノロジーで解決できる自社の課題要素を知る
まずは、“知”らなければ何も始まらない。「テクノロジーで何が実現できるか」など、数あるテクノロジーを現実で見て触れ、知見を広げていく。また、プロジェクトを組んでメンバーに知るべきテクノロジーを研究させる方法などがある。【図表2】は3Dプリンターの技術解決要素を棚卸ししたフレームワーク例である。
【図表2】Techno Drivenフレームワーク(3Dプリンター技術の例)
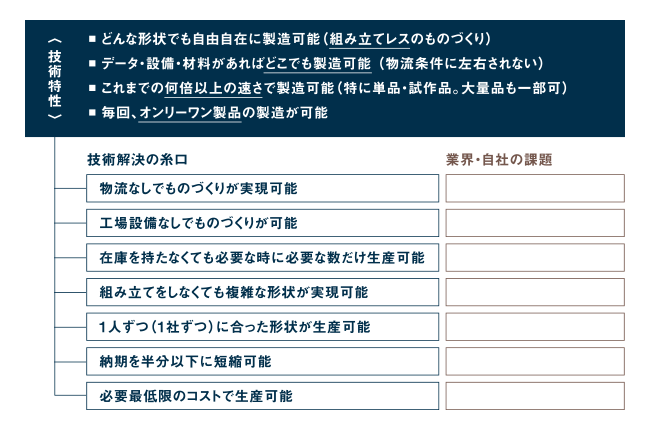
出所:タナベ経営が作成
②テクノロジーで解決すべき自社の課題を抽出する
考え方は大きく「攻め」と「守り」に分けることができる。最初に着手しやすいのは「守りの施策」だ。
守りの施策とは、「人が行う作業をテクノロジーに置き換える」ことを言う。人口減少に悩む日本において、ルーティンワークをテクノロジーに置き換えることは、ある種決まった未来とも言える。つまり、そこに取り組まなければ企業競争力は下がるのだ。
「攻めの施策」とは、「顧客価値」を上げる取り組みである。BtoCビジネスの事例として、動画配信サービスがある。動画の視聴はオンラインが当たり前の時代となり、「いつでもどこでも好きな動画を視聴できる」という新たな価値提供を実現している。
BtoC、BtoBどちらの事例にも共通するのが、「顧客の悩みを解決している」ことである。顧客視点に立ち、さまざまなテクノロジーを用いて課題解決の手段を模索し続けていただきたい。
③TVMにまとめる
テクノロジーを用いた課題解決のアイデアを時系列順に整理することで、全社の共通判断軸となるTVMが完成する。整理する際には、①取り組みたい部署から始める、②守りの施策を始める、③攻めの施策を始める、という3つのステップを踏んでいただきたい。
ここで肝要なのが、①である。デジタル化への変化を拒む組織・人は少なくない。デジタル化に前向きな部署から始め、その取り組みを他の組織に伝播させ、組織風土や個人の考え方を変革していく流れをつくることが理想だ。また守りの施策から始めることで、DXに取り組むための余力を生み出し、そのまま攻めの施策につなげることができる。
まずは、テクノロジーを“知る”ことから始める。その後、Techno Drivenで自社の解決すべき課題を抽出し、テクノロジーを用いてビジネスモデルや組織を変革いただきたい。

タナベ経営の研究会とは、同じ顧客課題の解決に取り組む仲間とともに、視察先企業や最新の企業事例を通じて、ビジネスモデルやマネジメント手法を研究するプラットホームです。