有事における「働き方改革」:山内 優和
「改善」から「改革」へ
新型コロナウイルス感染防止のため日本政府より発出された「緊急事態宣言」により、時差出勤やテレワークなどが多方面で推奨される中、対応に踏み切れない企業が多い。テレワークで対応可能な業務にもかかわらず出社する、これまでの業務形態の成功体験から業務のデジタル化に抵抗感を覚えてしまう――。日本企業の強みは、「改善」に向け勤勉に粘り強く頑張れるというマインドにあるが、有事においてはそれらの強みがネックとなりかねない。
今、日本企業に必要なのは待ったなしの「働き方改革」=「生産性改革」である。私たちが進むべき道は、「改善」より「改革」。自社がこれまで取り組んでいないこと、つまり、過去の延長線上にない新たな取り組みこそが「改革」である。有事を乗り越えるには「改革」マインドが必要なのだ。
本稿では、この「待ったなし」の状況における働き方改革の在り方をご紹介したい。
デジタル化の積極的な推進
アナログで行う業務はあまりにも時間のロスが大きい。例えば、手書きの発注書を作成すると1枚につき約30分かかる。このような業務を、RPA(Robotic Process Automation:一連の作業を自動化するソフトウエア)に任せれば数分で終わらせることができる。
世の中にある便利なITツールを、「ITに疎いから」と遠ざける方も少なくないだろうが、その場合はITにたけた社員に改善業務を任せてはいかがだろうか。
年商20億円の製造業A社にはIT関連部門がなく、多くの業務がアナログ形式だった。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響でテレワークの導入が喫緊の課題となり、30歳のB氏をデジタル推進リーダーに急きょ抜てき。B氏は設備保全が主な業務で、社内においてIT業務に関与することはこれまでなかったが、プライベートではAIや自作PC(パソコン)への造詣が深く、テレワーク導入時に大いにリーダーシップを発揮した。
ITに疎いという理由でテレワークの導入が進まないのであれば、社員の中でIT方面に長けた人材を探して活用するのも一策である。
Zoomやベルフェイスなどのウェブ会議システムも、いまや「やらざるを得ない」環境下に置かれた企業で導入が進んでいる。ウェブ会議はインターネット環境とカメラ付き端末があれば簡単に始められ、これにより直接人と会わずとも商談や打ち合わせができる。「導入がこんなに簡単だとは知らなかった」「時間と交通費をかけて訪問しなくても済む」との声が相次いでいる。
導入が進んだ背景には、IT技術の進展もさることながら、「どうせできない」から「やればできる」へ、体感マインドをリセットできたことがある。
一方、ITツールへの不得手感よりテレワーク導入時の勤怠管理に懸念を示す経営者も多い。そんな方々へは、C社の事例を紹介したい。C社では、始業時・終業時の報連相を徹底。1日に複数回、メールやメッセージ、電話を通じて上長と部下がコミュニケーションをとることで、業務内容と成果を共有している。
また、「MeeCap(業務の可視化、自動分析ツール)」などの業務効率化ソフトを導入し、PC操作を記録、集積、分析して業務改善を推進している。MeeCapをインストールしたPCでは、タイピングデータが記録されるため勤務状況を遠隔で把握できる上、業務効率の良い社員の仕事の仕方を共有化し、社内全体の業務効率を上げることもできる。
【図表】D社営業部門の業務ポジショニングマップ
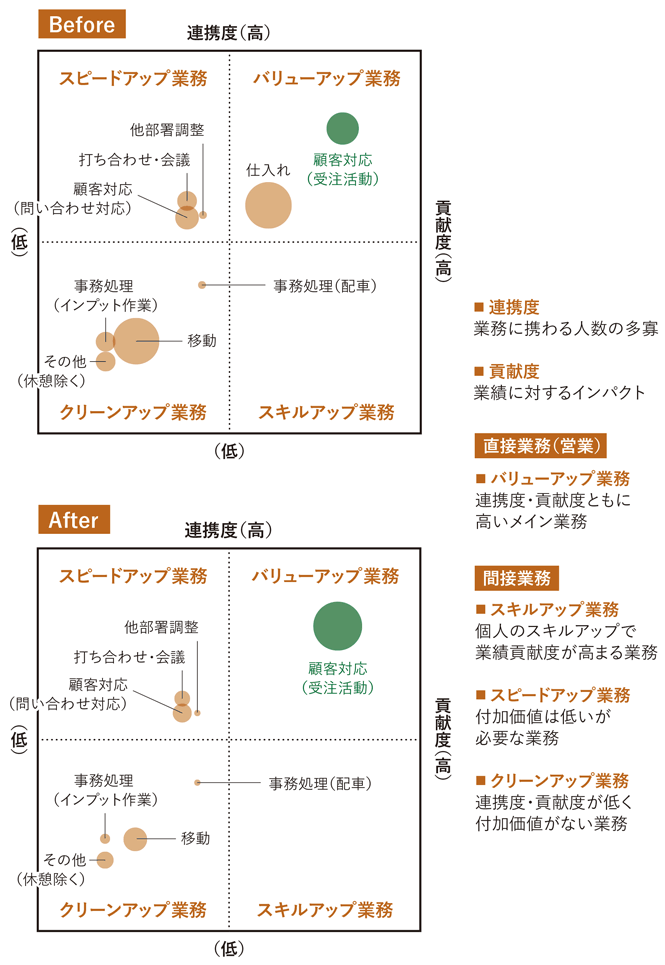
※円の大きさが業務時間に比例
出所:タナベ経営作成資料より筆者が加工・修正
聖域なき生産性改革
デジタル化は業務改善を伴うことが望ましい。業務の排除や過剰品質を改めるといった経営資源のインプット(コスト・時間)を減らすアプローチだけでなく、インプットを増やしてでもアウトプット(売上高・利益・キャッシュ)を最大化していくというアプローチが必要である。インプットを削るだけでは追い付かないのが現状だ。事例として、私がコンサルティングをしたD社の業務改善事例を紹介しよう。
D社は新型コロナウイルス対策で営業活動などに制限がある中、平常時は日々の業務に忙殺され取り組めていなかった業務改善に着手した。分析項目は、「業務フロー分析」「タスク分析」「業務棚卸分析」「活動時間分析」「業務ポジショニング分析」の五つである。
このうち営業部門では、業務ポジショニング分析(【図表】)を行った。その結果、バリューアップ業務のうち顧客対応(受注活動)が約14%しかなく、受注活動への時間配分不足が最大の課題であることが浮かび上がった。「本来は購買部門で行うべき仕入れ」「社用車を使った顧客先への移動」「エクセル・手書き中心の事務処理」の三つの業務に時間配分していたことが理由だった。
この課題に対し、「業務目的の再設定・配分」「Zoomを使ったウェブ商談導入による移動時間短縮」「RPA活用による定型業務の自動化」を提案し、労働時間を約2割削減しつつバリューアップ業務への時間配分を約4倍にすることができた。
有事の際は、経営者・経営幹部がリーダーシップを発揮することが最も大切である。改善から改革へマインドをリセットし、ためらうことなく「働き方改革」を推し進めていただきたい。






