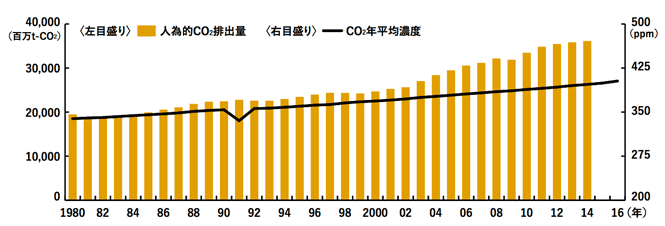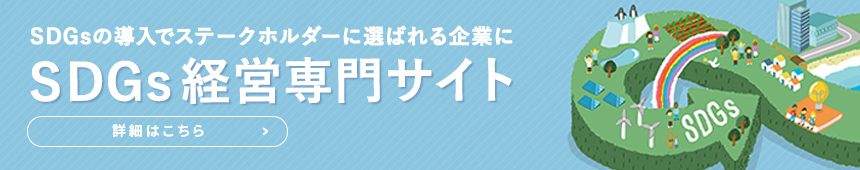社会課題への取り組みが共感を生む:井上 禎也
【図表】CO2の大気中濃度と人為的排出量
各国企業が取り組むSDGsとは
2015年に国連加盟国193カ国が全会一致で採択した、“ 誰一人取り残さない”世界の実現に向けた国際目標「SDGs(Sustainable DevelopmentGoals: 持続可能な開発目標)」。2030年を目標達成年とし、「貧困の撲滅」「飢餓撲滅、食糧安全保障」をはじめ17のゴールを掲げている。
SDGsの頭文字のS「サステナビリティー(持続可能性)」は従来、企業が収益を上げ、顧客からの信頼を得て存続し続けるという意味で使われることが多かった。しかし、現在は地球環境の問題を解決するための活動を指す言葉として、広く使われるようになってきている。
いまさら説明するまでもないことだが、例えば温暖化により海面上昇が起これば、人々の住む土地が水没する。廃棄プラスチックが海洋汚染を引き起こせば、水産物が取れなくなる。年々増え続けている人為的CO2排出量(【図表】)は自然環境悪化の要因の一つとなり、私たちの生活をおびやかす可能性が高い。SDGsはこうした課題に企業が取り組んでいくべきという考え方である。
この国際目標を達成するため、日本においてもさまざまな企業が施策を打ち出している。日本郵便は、環境に配慮した低排出ガス車両を導入したり、郵便局の照明設備をLED化したり、荷物を受け取る方法を増やすことで再配達を減らしたりして、CO2排出量の削減に取り組んでいる。
またネスレ日本は、人気チョコレート菓子「キットカット」について、2019年9月下旬から大袋の外袋を紙パッケージに切り替えた。これにより年間約380tのプラスチック削減を見込んでいるという。
海外企業の取り組み事例
欧州では、環境保護を企業の存在価値と捉える人も少なくない。環境問題に取り組んでいない企業は、存続すべきではないとの考えもあるほどだ。そのため欧州諸国の企業は、特に環境問題に対して積極的な取り組みを行っている。
例えば、タナベ経営アグリビジネスモデル研究会の海外視察で訪れたオランダのパプリカ生産者・バーレンセDCは、気候変動に対する取り組みが進んでいる。広大なグリーンハウスでオレンジパプリカを大量生産している同社は、自家発電によって発生したCO2をハウスに供給。さらに、天然ガスで自家発電した余剰電力を近隣の事業所に売電したり、その事業所で発生した熱をハウスに供給して温度を保ったりといった仕組みによって、環境資源の循環を実現していた。
また、あるレストランでは、SDGsの目標の一つである「海の豊かさを守る」ことを目的に、可能な限り天然物よりも養殖物の食材を採用。その養殖場での品質向上まで支援している。
米国企業の事例としては、アウトドア製品・ウエアの製造を手掛けるパタゴニアを挙げたい。同社は優れた耐久性を持ち、かつリサイクル可能な素材を用いた商品を、同業他社より高価格で販売している。これは、自社製品で決して地球環境を汚さないという姿勢の表れだ。モノを作り、消費者に届けるというメーカーの立場をうまく活用し、地球環境保護の考え方を普及することを徹底している。
同社は、あるキャンペーンの際、「自社の製品を買うな」という広告を出し、「本当に必要なものだけを購入するように」と消費者に呼び掛けたことがある。これが企業の経営活動において正しいかどうかは議論の分かれるところだが、消費者の無駄な消費を抑え、環境に悪影響を与える製品を少なくすることで、地球環境の保護に協力したいというサステナビリティーの精神に基づく企画であった。
この広告を掲げた後、どうなったか。同社の翌日の売り上げは13%伸び、さらにその翌営業日には28%も伸びた。同社の理念に共感し、自分も環境保護のために貢献したいと考えた消費者が、あえて製品を購入するという行動に至ったとみられている。結果、他のどのようなプロモーションよりも、自社ファンを創出したのである。
企業のコンセプトがファンをつくる
消費者の好む商品・サービスを効率的に生産、あるいは調達して提供するマーケット・インの発想が大事なのは言うまでもない。しかし、パタゴニアの例から分かるように、近年はサステナビリティーの考え方を前提として自社の存在意義から経営方針を定め、それに共感してくれるユーザーと付き合っていくという潮流がある。
サステナビリティーは、短期的な視点では収益につながりにくい。だが、この考え方を踏まえた企業コンセプトを掲げなければ、今後の優良顧客・長期顧客となり得る“ 共感ユーザー”を創出することは難しい。サステナビリティーは今、自社の存続に影響を与えるほど重要な要素なのだ。世界規模の環境課題に対して企業として何ができるのか、一度立ち止まって考える価値はあるだろう。
日本国内にも多くの社会課題がある。他社との差別化が図れないと悩んでいる企業こそ、この課題解決に踏み出してはどうか。自社の企業コンセプトや商品・サービスが、世の中の課題を解決できるものなのか、いま一度、見直していただきたい。