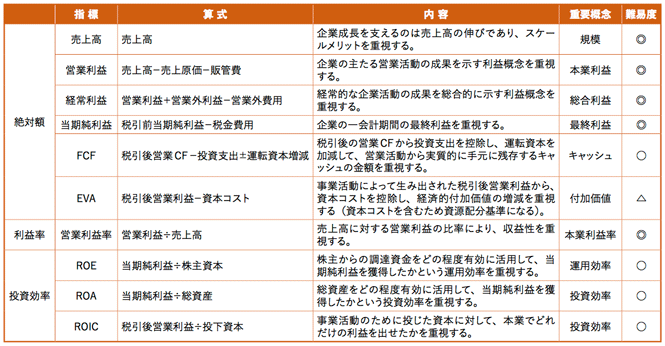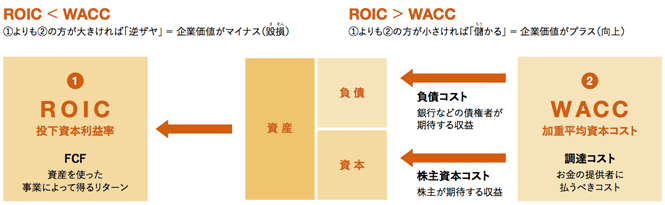事業評価指標による
ポジション別の事業戦略判断(後編):鈴村 幸宏
ROIC経営によるファイナンス思考
ROAやROEは、キャッシュ(現金)の流れや調達コスト(資本コスト)の視点が欠如しているとの考え方から、キャッシュフロー重視の「FCF」(フリーキャッシュフロー=自由に使える現金の量)や、企業の資本コスト重視の「EVA」(経済的付加価値)、「ROIC」という指標が、上場企業を中心に重要視されてきている。
このうちROICは、投下資本をバランスシート(貸借対照表)の借方、貸方のいずれで捉えるかによって、定義付けは異なる。投下資本を「投資家から調達した資本」と捉える場合は、調達サイド(貸方)の「有利子負債+自己資本」を投下資本(?)と捉えるのが一般的である。一方、「実際に事業で活用している資本」と捉える場合は、バランスシートの運用サイド(借方)の「運転資本+固定資産」を投下資本(?)と定義する。
本来、両者は一致すべきであるが、現実には非事業資産がバランスシートに含まれていることが多く、「有利子負債+自己資本」=「運転資本+固定資産」とはならない。そのため全社のROICは投下資本?、事業別ROICは投下資本?で計算されるケースが多い。
ROICに対応する資本コストは、「WACC」(加重平均資本コスト)である。これは企業全体の資本コストで、借り入れに要するコスト(負債コスト)と株式調達にかかるコスト(株主資本コスト)を加重平均して算出される。端的に言うと、資金を1円調達するのにコストがいくらかかっているかを示す。
ROICからWACCを差し引いたものを「ROIC Spread」と呼ぶ。ROICがWACCを上回っていれば、資本提供者にとって企業価値が創造されていると言える。(【図表2】)
「会社の企業価値を最大化するために、長期的な目線に立って事業や財務に関する戦略を総合的に組み立てる考え方」をファイナンス思考と言い、ROICを重視したROIC経営はファイナンス思考の経営と言える。
ROICによる投資判断と事業評価指標の選択
ROAやROEの計算式は非常にシンプルであり、有価証券報告書などの公表情報を利用して簡単に計算することができるため、他社との比較性という面ではROICよりも優れている。また、現場への展開という点では、ROEよりもROAとROICは両方とも優れている。
しかし、投資家はROAよりもROICを重視している。これは、ROICが資本コストとの比較で評価される指標であり、資本市場を意識した経営にとって有用な指標だからである。
ROICは有利子負債と自己資本で調達した資金を事業に投資した結果、得られるリターンの比率を表す指標であることから、事業資金の提供者である金融機関と株主の期待収益率を加重平均したWACCと比較することで、資本提供者の期待を上回ったか否かが評価される。これに対してROAは、調達サイドに事業負債が含まれていることから、資金調達コストとの比較でパフォーマンスを評価するのは困難である。このため、資本コストを上回るリターンを企業に期待する投資家は、資本コストが評価の基準となるROICを重視した経営を期待する。すなわち、ROICは、投資判断の指標として優れているということである。
もっとも、どの事業評価指標も長所と短所があり、評価の切り口が異なっている。売り上げの伸長を目指す時、コスト削減を徹底すべき時、また投資家への説明責任を重視すべき時など、自社の現状をよく見て、中長期的な視点から、いま必要とされる事業評価指標を選択し、事業に対する投資・撤退を判断していただきたい。
最後に、本件について、さらに知見を深めたい方は、CFOの職務の全容を体系的に捉え、実務でも活用できるよう学びを深める「戦略CFO研究会」(タナベ経営主催)にご参加ください。